天狗和尚(茨城町)
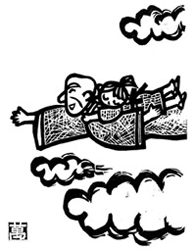
東茨城郡茨城町下土師に、慈雲寺という曹洞宗のお寺があります。
むかし、この寺にタイニン和尚という一風変わったお坊さんがおりました。
出かける時は、いつも一本歯の高下駄をはき、六貫目(約二十二・五キログラム)*1もある鉄棒を持ち歩いているのです。
寺には小僧も置かず、気ままな一人暮らしで、自分で食事を作るのが面倒な時には、村人に「ちょっと兄寺のところで飯をごちそうになってくる。」と言ってはよく出かけて行きました。
この兄寺というのは小川(東茨城郡小川町)の天聖寺で、慈雲寺からは三里(約十二キロメートル)*2ほども離れているにもかかわらず、和尚は今出て行ったかと思うとすぐに帰ってくるのです。
(不思議だな。和尚さんは、空でも飛んでるんじゃないのか?)・・・・・・村人は半ば冗談でそんなうわさをしておりました。
ところがある日、それを裏づけるような出来事がありました。
和尚さんが村の子供を連れて、尾張国(現在の愛知県)津島の祇園祭*3を見物に行き、一夜のうちに戻ってきたのです。
その子供に話を聞くと、「和尚さんにおんぶされ、向こうに着くまでは絶対に目を開けてはいけないよといわれたんだ。少しして和尚さんが背中からおろしてくれたので、そっと目を開けたら、もう着いていた。津島の祇園祭はすごかったよ。あんなきれいなお祭り見たことないや。」というのです。
「やっぱり和尚さんは天狗様だったのだ。」うわさは、またたく間に村中に広まり、それ以来、この和尚を「天狗和尚」と呼ぶようになったのだそうです。
前回(三十七話)の「愛宕神社の奉納相撲」でというお話で、十人抜きをして優勝したお坊さんは、この天狗和尚だといわれています。
- *1 貫
- 尺貫法の重さの単位、1貫は3.75キログラム。
- *2 里
- 地上の距離の単位、1里は約3,927メートル。
- *3 津島の祇園祭
- 祇園祭とは祇園会のことで京都の八坂神社の祭礼を指す。現在、津島市には祇園祭と呼ばれる祭礼はない。津島市を代表するお祭りに、「尾張津島天王祭」(津島神社の祭礼として500年の伝統を誇る夏祭りで日本三大川まつりのひとつ。現在は7月第4土曜と翌日の日曜)と「尾張津島秋まつり」(こちらも300年近い歴史のあるお祭りで絢爛豪華な山車が練り歩く。現在は10月の第1日曜と前日の土曜)がある。このいずれかにあたるのではないかと推測されるが、確かなことは不明。
-
参考資料
- 「茨城町史・地誌編」(茨城町)
「茨城の伝説」(今瀬文也・武田静澄共著)
「茨城の史跡と伝説」(茨城新聞社編)
「いわまの伝え話」(岩間町教育委員会)
「郷土資料事典・愛知県」(人文社)
「日本の祭り事典」(田中義広編)
「津島市ホームページ・観光」

