六地蔵が七地蔵に(水戸市)
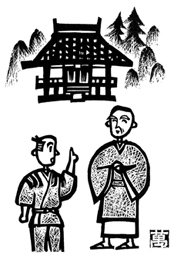
水戸市六反田町の六地蔵寺は、真言宗のお寺で、安産・子育てにご利益があるとして広く信仰されています。
境内には見事なしだれ桜があり、花の名所としても知られ、特に開花期には多くの参拝者でにぎわいます。
お寺の名前は、ご本尊*1が六体の木像地蔵尊であることから付いたといわれています。
今回は、その六地蔵寺のご本尊が七体になってしまったというお話です。
むかし、村人がお寺にお参りに行くと、六体あったお地蔵様が五体しかないのに気付きました。
不思議に思って、和尚さんにたずねると、「ああ、そのお地蔵様なら唐*2の金山寺が火事だというので、消火の手伝いに出かけているのだよ。」と事もなげにいうのです。
それを聞いた村人たちはびっくりしましたが、「六地蔵寺にお地蔵様が五体しかないのはおかしいだろう。」と仏師*3に頼んで一体を作りお寺に奉納しました。
「よかった、よかった。これで元通りになった。」と村人たちはほっとしておりましたが、しばらくすると、さらに驚くことが起きました。
唐に火消しに行っていたお地蔵様が戻ってきたため、お地蔵様が七体になったというのです。
それ以来、「六地蔵寺の七地蔵」として有名になり、ますます人々の信仰を集めたということです。
-
*1 本尊
- 寺院の本堂に安置し、崇拝の中心となる仏。
- *2 唐
- 中国・朝鮮の古称。また、広く外国の意。
- *3 仏師
- 仏像を作る職人。
-
参考資料
- 「茨城の伝説」(今瀬文也・武田静澄共著)
「水戸の民話」(藤田稔編著)
「茨城の寺を訪ねて」(茨城放送)

