強飯をはこぶ小僧(城里町)
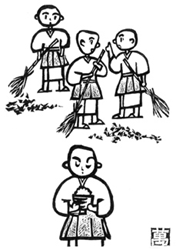
東茨城郡城里町下古内に、佐竹氏の菩提寺として栄えた臨済宗*1の名刹*2「清音寺」があります。
むかし、この寺で数十人の小僧さんが熱心に修行に励んでおりました。その中に一人、たいそう顔立ちの美しい少年がおりました。
その小僧さんは、毎日どこからか強飯(おこわ)*3を運んで来ては、ご本尊の観音さまにお供えしておりました。
でも、修行はとても真面目にするのですが、口数が少なく、人とあまり話をしないので、強飯をどこから持ってくるのかは誰も知りませんでした。
ある日のこと、清音寺から一キロメートル余り離れた藤井川の龍譚淵に、村の領主が魚釣りにやって来ました。
しばらくすると、魚信があり、かなりの大物と思われる手ごたえに領主は大喜び。
悪戦苦闘の末に上げてみると、それは一丈(約三メートル)もある大ウナギだったのです。
そのウナギを料理しようと腹を割くと、中には強飯がぎっしりと詰まっておりました。
これには領主もおどろき、「このウナギは藤井川の主に違いない。」と、川のほとりにねんごろに埋葬したのです。
この出来事とちょうど同じ頃、他にも不思議なことが起こっておりました。
強飯を運んではご本尊に供えていた小僧さんが寺からぷっつりと姿を消してしまったのです。
それを聞いた村の人々は、「あの小僧さんは大ウナギの化身*4だったのではないか。」とうわさし、ウナギを埋葬した場所に石のお地蔵さまをたてて供養しました。
そのため、このお地蔵さまは「ウナギ地蔵」と呼ばれるようになったのだそうです。
-
*1 臨済宗
- 禅宗の一派。唐の臨済を開祖とする。日本では鎌倉時代に栄西が伝えたのに始まり、室町幕府は京都・鎌倉に五山を定めて保護した。現在15派に分かれる。
- *2 名刹
- 名高い寺院
- *3 強飯
- もち米を蒸したもの。多くは小豆を加え祝賀に用いる。仏事には小豆を加えない白いもの、又は黒豆を混ぜた強飯を用いる。おこわ。赤飯。
- *4 化身
- 神仏・異類・鬼畜などが人間の姿をとって現れたもの。
-
参考資料
- 「常北町史」(常北町)
「茨城の伝説」(今瀬文也・武田静澄共著)
「いばらきのむかし話」(藤田稔編)
「茨城の史跡と伝説」(茨城新聞社編)

