金色姫(つくば市)
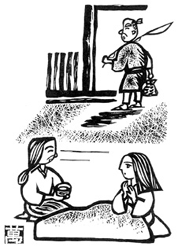
そのうち姫は、お后に命じられた家来に獣のすむ山に置き去りにされたり、草木も生えない島に流されるなど、四度も恐ろしい目にあわされ、命を失いかけました。でも、そのたびに運よく助けられ、無事御殿に戻って来たのです。
姫をふびんに思い、行く末を心配した王さまは悩みぬいた末、「どこかほかに良い国があろう。そこに行って幸せに暮らしなさい。」と、姫を桑の木でつくった丸木舟に乗せて海に流したのです。
流れ流れて舟がたどりついたのは、むかしは岬であったという筑波山麓の豊浦(現在のつくば市神郡地内)という所でした。そこで姫は心優しい権太夫とその妻に助けられて元気をとりもどし、平穏な日を過ごしておりました。
ところが姫はそれまでの疲れのためか、まもなく体調をくずして死んでしまったのです。
姫をわが子のようにかわいがっていた権太夫夫婦は、嘆き悲しみながら姫のなきがら*4を棺*5におさめました。
あくる日、権太夫が棺を開けてみると、そこに姫の姿はなく、小さな白い虫がいるだけでした。
『この虫は姫の生まれかわりに違いない。』そう考えた権太夫が虫に桑の葉を与えてみると喜んで食べ、日に日に大きく育っていきました。
しかし、虫はその間、桑の葉を食べず眠りにつき、眠りから覚めてはまた食べるということを四度繰り返しました。やがて口から白い糸を吐き、それが白い繭*5となったのです。
ある晩のこと、権太夫の夢の中に筑波の神さまが現れ、繭から絹糸をとる方法を教えてくれました。それが養蚕*7の始まりで、以来、この地方に養蚕が広まり盛んになったのだそうです。
つくば市神郡にある蚕影(蚕影山)神社は、古くから養蚕の神さまとして多くの信仰を集めてきましたが、養蚕農家が減ってしまった今は参拝する人も少なくなってしまいました。
これと同じような話が、神栖市日川の「蚕霊神社」と日立市川尻町の「蚕養神社」にも伝えられています。
-
*1 王女
- 王の娘。
- *2 后(きさき)
- 皇帝や王侯の妻。
- *3 継母
- 親子の血のつながりのない母。父の後妻。
- *4 なきがら
- 死体。魂のぬけがら。
- *5 棺(ひつぎ)
- 死体をおさめて葬る木製の箱。
- *6 繭(まゆ)
- 特に蚕の繭。俵形・球形・楕円形などある。いずれも生糸の原料。
- *7 養蚕(ようさん)
- 蚕(かいこ)を卵から飼い育てて繭をとること。
-
参考資料
-
「茨城の伝説」(今瀬文也・武田静澄共著)
「筑波町の昔ばなし」〈下〉(仲田安夫著)
「いばらきのむかし話」(藤田稔編)
「常陽藝文 二〇〇一/十二月号」(財団法人常陽藝文センター)

